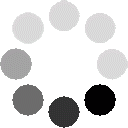プリズンホテル〈1〉夏
×
Success!
×
Error!
×
Information !
Rights Contact Login For More Details
- LEE's Literary Agency
- https://www.pubmatch.com/lees.html
More About This Title プリズンホテル〈1〉夏
- English
- Chinese (Traditional)
English
極道小説で売れっ子になった作家・木戸孝之介は驚いた。
たった一人の身内で、ヤクザの大親分でもある叔父の仲蔵が温泉リゾートホテルのオーナーになったというのだ。
招待されたそのホテルはなんと任侠団体専用。
人はそれを「プリズンホテル」と呼ぶ―。
熱血ホテルマン、天才シェフ、心中志願の一家…不思議な宿につどう奇妙な人々がくりひろげる、笑いと涙のスペシャル・ツアーへようこそ。
たった一人の身内で、ヤクザの大親分でもある叔父の仲蔵が温泉リゾートホテルのオーナーになったというのだ。
招待されたそのホテルはなんと任侠団体専用。
人はそれを「プリズンホテル」と呼ぶ―。
熱血ホテルマン、天才シェフ、心中志願の一家…不思議な宿につどう奇妙な人々がくりひろげる、笑いと涙のスペシャル・ツアーへようこそ。
Chinese (Traditional)
◎日本狂銷160萬冊之極道小說系列傑作
◎日本直木賞國民天王淺田次郎代表作
◎爆笑式療癒系小說!
江湖四海齊聚一堂.歡笑血淚一齊暴走
他們,因迷失而來到這裡,卻也在這裡尋回人生
歡迎光臨! 極道樂の天堂
性格扭曲的極道作家、被迫扮演作家筆下主角的苦命情婦、慈愛卻逆來順受的天兵繼母、俠義卻也柔情的黑幫老大、來自東南亞的旅館服務生、一群不可思議的男女、一段笑淚縱橫的假期、一個充滿歡笑血淚的溫馨故事。
不景氣時代的爆笑求生術
熱血免錢!揍人有理!
搞不定的事
來監獄飯店喬一下就對了
知名黑道小說家木戶孝之介,在父親法事上聽到一個驚人的消息:他唯一的血親叔叔--黑道大哥的仲藏,竟成了溫泉度假旅館的大老闆。而且這間飯店招待的幾乎都是道上弟兄,所以被當地人稱為「監獄飯店」。算計著將成為飯店接班人的木戶,帶著情婦阿清一起前往飯店度假兼寫作。曾是大哥女人的阿清,對黑道內幕知之甚詳,於是成為木戶蒐集題材最佳諮詢對象,加上個性逆來順受,常被迫配合木戶演出小說中的女主角。
只是沒想到,飯店竟聚集了一群牛鬼蛇神。掌櫃黑田原是暴走族,現在擔任仲藏老大的左右手。和式料理長梶平太郎是前代飯店主人雇用的廚師,個性孤僻,但手藝一流。服務生則是一群馬尼拉外籍勞工。當然,客人也不是省油的燈:關東櫻花會大曾根家一行人、一對來泡湯旅行的老夫妻,妻子準備向丈夫提離婚;生意失敗,準備自殺的一家人……巧的是,颱風也來湊熱鬧,大家只能待在飯店裡。一片漆黑中,刺客悄悄潛入,當槍聲響起,每個人內心壓抑許久的祕密不禁暴走……
◎日本直木賞國民天王淺田次郎代表作
◎爆笑式療癒系小說!
江湖四海齊聚一堂.歡笑血淚一齊暴走
他們,因迷失而來到這裡,卻也在這裡尋回人生
歡迎光臨! 極道樂の天堂
性格扭曲的極道作家、被迫扮演作家筆下主角的苦命情婦、慈愛卻逆來順受的天兵繼母、俠義卻也柔情的黑幫老大、來自東南亞的旅館服務生、一群不可思議的男女、一段笑淚縱橫的假期、一個充滿歡笑血淚的溫馨故事。
不景氣時代的爆笑求生術
熱血免錢!揍人有理!
搞不定的事
來監獄飯店喬一下就對了
知名黑道小說家木戶孝之介,在父親法事上聽到一個驚人的消息:他唯一的血親叔叔--黑道大哥的仲藏,竟成了溫泉度假旅館的大老闆。而且這間飯店招待的幾乎都是道上弟兄,所以被當地人稱為「監獄飯店」。算計著將成為飯店接班人的木戶,帶著情婦阿清一起前往飯店度假兼寫作。曾是大哥女人的阿清,對黑道內幕知之甚詳,於是成為木戶蒐集題材最佳諮詢對象,加上個性逆來順受,常被迫配合木戶演出小說中的女主角。
只是沒想到,飯店竟聚集了一群牛鬼蛇神。掌櫃黑田原是暴走族,現在擔任仲藏老大的左右手。和式料理長梶平太郎是前代飯店主人雇用的廚師,個性孤僻,但手藝一流。服務生則是一群馬尼拉外籍勞工。當然,客人也不是省油的燈:關東櫻花會大曾根家一行人、一對來泡湯旅行的老夫妻,妻子準備向丈夫提離婚;生意失敗,準備自殺的一家人……巧的是,颱風也來湊熱鬧,大家只能待在飯店裡。一片漆黑中,刺客悄悄潛入,當槍聲響起,每個人內心壓抑許久的祕密不禁暴走……
- English
- Chinese (Traditional)
English
浅田次郎[アサダジロウ]
51年東京生。「地下鉄に乗って」で第16回吉川英治文学新人賞、97年「鉄道員」で第117回直木賞、00年「壬生義士伝」で第13回柴田錬三郎賞受賞
51年東京生。「地下鉄に乗って」で第16回吉川英治文学新人賞、97年「鉄道員」で第117回直木賞、00年「壬生義士伝」で第13回柴田錬三郎賞受賞
Chinese (Traditional)
淺田次郎
原名岩田康次郎,1951年生於東京。高中畢業時,受三島由紀夫自殺的影響而加入自衛隊。期滿退役後,歷經各種工作,讓他擁有細膩多感的特質,豐富的生活經驗也形塑了他的寫作風格。1991年在他40歲時,以《被拿到還得了》一文初試啼聲。早期的作品是以黑道小說為主,1993年出版的《監獄飯店》系列即為代表作。1995年,他以《穿越時空.地下鐵》獲得吉川英治文學新人賞。1997年,更以《鐵道員》奪得日本文學大獎直木賞,奠定了他在日本文壇的地位。
其作品取材廣泛,文字風格多樣,除了現代小說、短篇散文,也有《蒼穹之昴》、《中原之虹》等以中國歷史為主題的長篇小說。有不少作品少成為電影或電視劇的題材,可說是傳承日本大眾文化的小說家。如《椿山課長的那七天》,他以幽默風趣的筆調嘲諷官僚制度的不合理,引人發噱,同時又能刻劃出親情及愛情,令人動容。又如《鐵道員》,改拍成電影後廣獲國際影壇注目,更將其文學推向世界。
淺田次郎曾說:「寫作是我最大的興趣」,在近20年的寫作生涯中,創作力源源不絕,出版了70多部作品,自稱「小說的大眾食堂」。讀者也著迷於其作品中平淡卻豐潤的人情味,封其為「平成催淚作家」。目前,他是多個文學獎審查委員,如直木賞、吉川英治文學新人賞、山本周五郎賞等。
原名岩田康次郎,1951年生於東京。高中畢業時,受三島由紀夫自殺的影響而加入自衛隊。期滿退役後,歷經各種工作,讓他擁有細膩多感的特質,豐富的生活經驗也形塑了他的寫作風格。1991年在他40歲時,以《被拿到還得了》一文初試啼聲。早期的作品是以黑道小說為主,1993年出版的《監獄飯店》系列即為代表作。1995年,他以《穿越時空.地下鐵》獲得吉川英治文學新人賞。1997年,更以《鐵道員》奪得日本文學大獎直木賞,奠定了他在日本文壇的地位。
其作品取材廣泛,文字風格多樣,除了現代小說、短篇散文,也有《蒼穹之昴》、《中原之虹》等以中國歷史為主題的長篇小說。有不少作品少成為電影或電視劇的題材,可說是傳承日本大眾文化的小說家。如《椿山課長的那七天》,他以幽默風趣的筆調嘲諷官僚制度的不合理,引人發噱,同時又能刻劃出親情及愛情,令人動容。又如《鐵道員》,改拍成電影後廣獲國際影壇注目,更將其文學推向世界。
淺田次郎曾說:「寫作是我最大的興趣」,在近20年的寫作生涯中,創作力源源不絕,出版了70多部作品,自稱「小說的大眾食堂」。讀者也著迷於其作品中平淡卻豐潤的人情味,封其為「平成催淚作家」。目前,他是多個文學獎審查委員,如直木賞、吉川英治文學新人賞、山本周五郎賞等。
- English
English
試し読みは
「おめえでさえ世間様から先生なんて呼ばれるんだぜ。この俺がリゾートホテルのひとつやふたつブッ建てたって、何のフシギもあるめえ」
――仲蔵親分は偏屈な小説家に向かって言った。
気の遠くなるほど退屈な読経が終わって、参会者が住職に導かれて墓に向かったあと、ぼくは富江の襟首をつまんで本堂の縁側に連れ出した。
そこが寺でなくて、父の七回忌の席でなかったら、ぼくはたぶんいつものように富江を殴りとばしていたことだろう。
ぼくは子供のころからずっと、この齢の違わぬ義母を呪っていた。殴っても殴っても、殴り足らぬほど憎んでいた。
そんな言い方をすると、何だか通りいっぺんの苦労話のようで、ぼくがいわゆる継母にいじめ抜かれて育ったように聞こえるかもしれないが、あいにく富江に継子いじめをするような甲斐性はない。
富江はグズでノロマでブスで、齢より十歳も老けて見える。実際はぼくとひとまわりしか違わないから、今年ようやく四十七だというのに、見ようによっては六十のババアにも見えるのだ。
決して大げさな表現ではない。ぼくと富江の二人で住むマンションを訪ねた出版社の連中は、ほぼ例外なく実の母親と勘ちがいするのだから、そのおそろしい老けこみようがぼくひとりの思いこみでないことは確かだ。
もとは父の経営していた町工場の女工兼女中であったものが、どういう成り行きかよくは知らんが父の後添いに収まった。ぼくが九つの時であったから、富江ははたちかそこいらで嫁に来たことになる。
ところがそのころのぼくの目に、富江はやはり三十すぎに見えた。たぶん誰が見てもそうだったんじゃないかと思う。
ひどい東北訛りで、斜視で、化粧ッ気なんか全然なくて、ぼくや父のそれと区別のつかないぐらいでかいパンツをはいていた。いちど間違えて学校にはいて行き、小便をするときに初めてそうと気付いたときのおぞましさといったらなかった。生涯わすれ得ぬ青春の痛手だった。
以来、ぼくはぼくの身の上に起こるすべての災難を、富江のせいにするようになった。いや、正しくはそうと決めた。
本堂の縁側からは、庭つづきの駐車場が望まれた。あじさいの生け垣に囲まれて、仲オジの白い乗用車がひときわ目につく。
「なんでおじさんを呼んだんだ」
ぼくは肩越しに親指を立てて車を指さし、富江を詰問した。斜視のまなこを昔のセルロイド人形のようにオロオロと動かして、しばらく言葉を探してから、富江は小声で答えた。
「だって、仲蔵さんしか身内がいないから。他人ばかりじゃあんまりみっともないと思って……」
「みっともないのは、おまえだよ」
と、ぼくは拳で富江の額をゴツゴツと小突きながら言った。「だいたい今どき法事なんてやることないんだ。うまい理由をつけて、工場の同窓会でもやる気だったんじゃないか」
「そんなことないよ孝ちゃん。みんなお父さんの世話になった人ばかりじゃないの……」
仲オジの乗用車には、人相の悪い若い衆が二人、ひとりはセッセと車を磨いており、年長らしいもうひとりは携帯電話で何やら良からぬ話をしている。
「まあ、それはいいとして。だが、あの仲オジとは一生付き合うなっていうのは、オヤジの遺言だ。たとえ血のつながりはあっても、ヤクザはヤクザだぞって、オヤジはいつも言っていた」
「でも、仲蔵さんももう齢だし、孝ちゃんにとってもたったひとりのおじさんでしょう。だから……」
「おまえな」、とぼくは尻すぼみになる富江の言葉を遮った。富江がぼくに対して口応えをするのは珍しいことだ。ぼくの胸のあたりまでしかない、しみだらけの首根っこを掴んで、ぼくは言った。
「あのな、おまえまた血圧高いんじゃないか。オラ、首揉んでやるから早いとこ血管切っちまえ。オヤジも待ってるぞ」
「やめてよ孝ちゃん」、と富江はちっとも色気のないしぐさで身をかわした。
「おめえでさえ世間様から先生なんて呼ばれるんだぜ。この俺がリゾートホテルのひとつやふたつブッ建てたって、何のフシギもあるめえ」
――仲蔵親分は偏屈な小説家に向かって言った。
気の遠くなるほど退屈な読経が終わって、参会者が住職に導かれて墓に向かったあと、ぼくは富江の襟首をつまんで本堂の縁側に連れ出した。
そこが寺でなくて、父の七回忌の席でなかったら、ぼくはたぶんいつものように富江を殴りとばしていたことだろう。
ぼくは子供のころからずっと、この齢の違わぬ義母を呪っていた。殴っても殴っても、殴り足らぬほど憎んでいた。
そんな言い方をすると、何だか通りいっぺんの苦労話のようで、ぼくがいわゆる継母にいじめ抜かれて育ったように聞こえるかもしれないが、あいにく富江に継子いじめをするような甲斐性はない。
富江はグズでノロマでブスで、齢より十歳も老けて見える。実際はぼくとひとまわりしか違わないから、今年ようやく四十七だというのに、見ようによっては六十のババアにも見えるのだ。
決して大げさな表現ではない。ぼくと富江の二人で住むマンションを訪ねた出版社の連中は、ほぼ例外なく実の母親と勘ちがいするのだから、そのおそろしい老けこみようがぼくひとりの思いこみでないことは確かだ。
もとは父の経営していた町工場の女工兼女中であったものが、どういう成り行きかよくは知らんが父の後添いに収まった。ぼくが九つの時であったから、富江ははたちかそこいらで嫁に来たことになる。
ところがそのころのぼくの目に、富江はやはり三十すぎに見えた。たぶん誰が見てもそうだったんじゃないかと思う。
ひどい東北訛りで、斜視で、化粧ッ気なんか全然なくて、ぼくや父のそれと区別のつかないぐらいでかいパンツをはいていた。いちど間違えて学校にはいて行き、小便をするときに初めてそうと気付いたときのおぞましさといったらなかった。生涯わすれ得ぬ青春の痛手だった。
以来、ぼくはぼくの身の上に起こるすべての災難を、富江のせいにするようになった。いや、正しくはそうと決めた。
本堂の縁側からは、庭つづきの駐車場が望まれた。あじさいの生け垣に囲まれて、仲オジの白い乗用車がひときわ目につく。
「なんでおじさんを呼んだんだ」
ぼくは肩越しに親指を立てて車を指さし、富江を詰問した。斜視のまなこを昔のセルロイド人形のようにオロオロと動かして、しばらく言葉を探してから、富江は小声で答えた。
「だって、仲蔵さんしか身内がいないから。他人ばかりじゃあんまりみっともないと思って……」
「みっともないのは、おまえだよ」
と、ぼくは拳で富江の額をゴツゴツと小突きながら言った。「だいたい今どき法事なんてやることないんだ。うまい理由をつけて、工場の同窓会でもやる気だったんじゃないか」
「そんなことないよ孝ちゃん。みんなお父さんの世話になった人ばかりじゃないの……」
仲オジの乗用車には、人相の悪い若い衆が二人、ひとりはセッセと車を磨いており、年長らしいもうひとりは携帯電話で何やら良からぬ話をしている。
「まあ、それはいいとして。だが、あの仲オジとは一生付き合うなっていうのは、オヤジの遺言だ。たとえ血のつながりはあっても、ヤクザはヤクザだぞって、オヤジはいつも言っていた」
「でも、仲蔵さんももう齢だし、孝ちゃんにとってもたったひとりのおじさんでしょう。だから……」
「おまえな」、とぼくは尻すぼみになる富江の言葉を遮った。富江がぼくに対して口応えをするのは珍しいことだ。ぼくの胸のあたりまでしかない、しみだらけの首根っこを掴んで、ぼくは言った。
「あのな、おまえまた血圧高いんじゃないか。オラ、首揉んでやるから早いとこ血管切っちまえ。オヤジも待ってるぞ」
「やめてよ孝ちゃん」、と富江はちっとも色気のないしぐさで身をかわした。