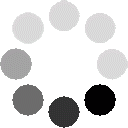プリズンホテル〈3〉冬
×
Success!
×
Error!
×
Information !
Rights Contact Login For More Details
- LEE's Literary Agency
- https://www.pubmatch.com/lees.html
More About This Title プリズンホテル〈3〉冬
- English
- Chinese (Traditional)
English
阿部看護婦長、またの名を“血まみれのマリア”は心に決めた。
温泉に行こう。
雪に埋もれた山奥の一軒宿がいい…。
大都会の野戦病院=救命救急センターをあとに、彼女がめざしたのは―なんと我らが「プリズンホテル」。
真冬の温泉宿につどうのは、いずれも事情ありのお客人。
天才登山家、患者を安楽死させた医師、リストラ寸前の編集者。
命への慈しみに満ちた、癒しの宿に今夜も雪が降りつもる。
温泉に行こう。
雪に埋もれた山奥の一軒宿がいい…。
大都会の野戦病院=救命救急センターをあとに、彼女がめざしたのは―なんと我らが「プリズンホテル」。
真冬の温泉宿につどうのは、いずれも事情ありのお客人。
天才登山家、患者を安楽死させた医師、リストラ寸前の編集者。
命への慈しみに満ちた、癒しの宿に今夜も雪が降りつもる。
Chinese (Traditional)
☆ 日本狂銷160萬冊之極道小說系列傑作
☆ 繼《鐵道員》、《椿山課長的那七天》後,日本直木賞國民天王淺田次郎又一感人鉅獻
☆ 在日本1993、1995及1999年曾兩度被改拍成電視劇,1996年也曾被改拍為電影。目前韓國也已有籌拍電影的計畫。
☆ 淺田作品中改編成電影、電視劇、舞台劇、漫畫次數最多的小說
飯店入住須知
一、本館已有萬全準備,若警察前來搜索或發生肢體衝突時,請保持冷靜並聽從人員指示。
二、本飯店的客房全面使用鐵製房門及防彈玻璃,敬請安心住宿。
三、若發現被逐出組織或不同家系等可疑人物,請立即與櫃檯聯繫。
四、請道上客人不要在大廳或走廊上「交朋友」。
黑道大哥木戶仲藏經營的深山溫泉紫陽花飯店,由於招待的客人大多為黑道團體,因此當地居民稱之為「監獄飯店」。
而老闆的姪子,也就是行為乖張的極道小說家木戶孝之介,這回為了躲避出版社編輯的催稿行動,便帶著情婦清子,兩人連夜坐車逃往監獄飯店。
隨著季節的變換,深山的監獄飯店也進入了寒冷的冬天。今晚,隨著嚴冬的大雪,飯店內又聚集了懷抱各式各樣煩惱的客人。其中包括總是和死神搏鬥、救人無數的護理長;因安樂死事件而遭受控告的醫生;為完成夢想不惜賭上一切的天才登山家;受到霸凌而進入深山尋死的少年......
然而,這一群凝視著生與死的人們,在搶救一名瀕死病患的過程中,重新體認了生命的價值。而孝之介也將在感動中正視自己無法擺脫的過去,重新啟動停留在少年時期的時間齒輪,對清子說出一生只有一次的真愛告白......
今晚,在白雪皚皚的冬山上,監獄飯店將譜出一曲笑淚交織的極道讚歌!
☆ 繼《鐵道員》、《椿山課長的那七天》後,日本直木賞國民天王淺田次郎又一感人鉅獻
☆ 在日本1993、1995及1999年曾兩度被改拍成電視劇,1996年也曾被改拍為電影。目前韓國也已有籌拍電影的計畫。
☆ 淺田作品中改編成電影、電視劇、舞台劇、漫畫次數最多的小說
飯店入住須知
一、本館已有萬全準備,若警察前來搜索或發生肢體衝突時,請保持冷靜並聽從人員指示。
二、本飯店的客房全面使用鐵製房門及防彈玻璃,敬請安心住宿。
三、若發現被逐出組織或不同家系等可疑人物,請立即與櫃檯聯繫。
四、請道上客人不要在大廳或走廊上「交朋友」。
黑道大哥木戶仲藏經營的深山溫泉紫陽花飯店,由於招待的客人大多為黑道團體,因此當地居民稱之為「監獄飯店」。
而老闆的姪子,也就是行為乖張的極道小說家木戶孝之介,這回為了躲避出版社編輯的催稿行動,便帶著情婦清子,兩人連夜坐車逃往監獄飯店。
隨著季節的變換,深山的監獄飯店也進入了寒冷的冬天。今晚,隨著嚴冬的大雪,飯店內又聚集了懷抱各式各樣煩惱的客人。其中包括總是和死神搏鬥、救人無數的護理長;因安樂死事件而遭受控告的醫生;為完成夢想不惜賭上一切的天才登山家;受到霸凌而進入深山尋死的少年......
然而,這一群凝視著生與死的人們,在搶救一名瀕死病患的過程中,重新體認了生命的價值。而孝之介也將在感動中正視自己無法擺脫的過去,重新啟動停留在少年時期的時間齒輪,對清子說出一生只有一次的真愛告白......
今晚,在白雪皚皚的冬山上,監獄飯店將譜出一曲笑淚交織的極道讚歌!
- English
- Chinese (Traditional)
English
浅田次郎[アサダジロウ]
51年東京生。「地下鉄に乗って」で第16回吉川英治文学新人賞、97年「鉄道員」で第117回直木賞、00年「壬生義士伝」で第13回柴田錬三郎賞受賞
51年東京生。「地下鉄に乗って」で第16回吉川英治文学新人賞、97年「鉄道員」で第117回直木賞、00年「壬生義士伝」で第13回柴田錬三郎賞受賞
Chinese (Traditional)
淺田次郎
1951年12月13日生於東京。高中畢業時,因三島由紀夫自殺事件的影響而加入自衛隊。退役後歷經各種工作,讓他擁有細膩多感的特質和豐富的生活經驗,形塑了其寫作風格。40歲時,以《被拿走還得了》一文初試啼聲。早期的作品以黑道小說為主,1993年首次出版的《監獄飯店》系列便是代表作。1995年,以《穿越時空.地下鐵》獲得吉川英治文學新人賞。1997年,更以《鐵道員》一舉奪得日本文學大獎直木賞,奠定了他在日本文壇的地位。
其小說取材廣泛,文字風格多樣,不少作品在日後成為電影或電視劇的題材,可說是傳承日本大眾小說文化的小說家。如《椿山課長的那七天》中,以幽默風趣的筆調嘲諷官僚制度的不合理,同時刻劃出真摯的親情及愛情,令人動容。又如《鐵道員》,改拍成電影後獲得國際影壇的注目,更將他的文學推向世界級。
在近20年的創作中,著作超過70本,自稱「小說的大眾食堂」。讀者也因為他作品中平淡卻溫潤的人情味,封其為「平成的催淚作家」。目前擔任多項文學獎審查委員,諸如直木賞、吉川英治文學新人賞、山本周五郎賞等。
得獎記錄
★1995年以《穿越時空.地下鐵》獲得第16屆吉川英治文學新人賞。
★1997年以《鐵道員》獲得第16屆日本冒險小說協會大賞.特別賞及第117屆直木賞。
★2000年以《壬生義士傳》獲得第13屆柴田鍊三郎賞。
★2006年以《切腹》獲得第1屆中央公論文藝賞、第10屆司馬遼太郎賞。
★2008年以《中原之虹》獲得第42屆吉川英治文學賞。
1951年12月13日生於東京。高中畢業時,因三島由紀夫自殺事件的影響而加入自衛隊。退役後歷經各種工作,讓他擁有細膩多感的特質和豐富的生活經驗,形塑了其寫作風格。40歲時,以《被拿走還得了》一文初試啼聲。早期的作品以黑道小說為主,1993年首次出版的《監獄飯店》系列便是代表作。1995年,以《穿越時空.地下鐵》獲得吉川英治文學新人賞。1997年,更以《鐵道員》一舉奪得日本文學大獎直木賞,奠定了他在日本文壇的地位。
其小說取材廣泛,文字風格多樣,不少作品在日後成為電影或電視劇的題材,可說是傳承日本大眾小說文化的小說家。如《椿山課長的那七天》中,以幽默風趣的筆調嘲諷官僚制度的不合理,同時刻劃出真摯的親情及愛情,令人動容。又如《鐵道員》,改拍成電影後獲得國際影壇的注目,更將他的文學推向世界級。
在近20年的創作中,著作超過70本,自稱「小說的大眾食堂」。讀者也因為他作品中平淡卻溫潤的人情味,封其為「平成的催淚作家」。目前擔任多項文學獎審查委員,諸如直木賞、吉川英治文學新人賞、山本周五郎賞等。
得獎記錄
★1995年以《穿越時空.地下鐵》獲得第16屆吉川英治文學新人賞。
★1997年以《鐵道員》獲得第16屆日本冒險小說協會大賞.特別賞及第117屆直木賞。
★2000年以《壬生義士傳》獲得第13屆柴田鍊三郎賞。
★2006年以《切腹》獲得第1屆中央公論文藝賞、第10屆司馬遼太郎賞。
★2008年以《中原之虹》獲得第42屆吉川英治文學賞。
- English
English
試し読み
ぼくは月のうち一週間か十日を、神田駿河台にある「山の上ホテル」で過ごす。
そう、昔から文化人の宿として有名な、そして現実にいつ行っても小説家の二人や三人はカンヅメになっている、あのクラシックホテルである。
べつに伊達や酔狂ではない。遁世して小説を書くにはまことに適した場所だからそうするのである。
東京のどまんなかにあるのに極めて閑静で、大学の図書館や古本屋街が近いから、とっさの資料調べにも事欠かない。小ぢんまりとしたサイズは落ち着くし、何よりもホテル側に、締切りに追われてカンヅメになっている作家に対する十分な配慮がある。いわば牢屋番としての配慮である。「文化人の宿」という伝統的なコンセプトがそれほど徹底しているというわけだ。たとえば近ごろ気付いたことなのだが、ここの従業員たちは客がカンヅメになって書いている原稿がいったいどこの出版社の依頼によるものかということまで知っているらしい。
業界の情報を把握しているのか、一読者としての推測であるかは知らない。だがともかく、ぼく自身が予約し、ひそかにチェックインし、自発的にカンヅメとなっていても、なぜか原稿の依頼主を知っているらしいのである。
この点はまさに神の配慮と言えよう。
古いホテルの窓に凩の鳴く夜のことだった。
ぼくはそつなく用意された作家専用の大机に向かって、〈哀愁のカルボナーラ〉のクライマックスに挑んでいた。
それは〈仁義の黄昏〉シリーズの大ヒットにより極道作家の烙印を捺されてしまったぼくが、アイデンティティーの回復を賭けて世に問う、ぶっちぎりの恋愛小説である。
なにしろヨーロッパに留学中の女性ヴァイオリニストが、かつての恋人である新聞社特派員と、ベネチアのサン・マルコ広場で偶然出会い、たちまち焼けぼっくいに火がついて地獄の恋に堕ちてしまうというのだ。
原稿の半ばまでは、すでに大日本雄弁社の編集者に渡してある。半ばといったって五百枚もあるから、先方が気に入ろうと気に入るまいと、もはや取り返しはつかない。
もちろんヤクザの出番はなく、銃声も聴こえず、お得意の法的医学的用語を駆使した露骨なセックス・シーンもない。古今の恋愛小説の定義に従い、物語はさしたる盛り上がりもなく、ただ哀しく美しく、ダラダラと進む。
数日後、件の編集者がすっ飛んできて、「そろそろマフィアが出てきますよね、そうですよね」と言ったので、すかさずバックドロップを決めてやった。
クライマックス・シーンは、ヴァイオリニストと新聞記者がたそがれのゴンドラに乗り、夕日に染まった「溜息の橋」の下で熱いくちづけをかわすのである。
――古いホテルの窓に凩を聴きながら、ぼくはうっとりと、恋人たちをいざなう船頭になっていた。
電話が鳴った。
ぼくは呪いの雄叫びを上げて原稿をまき散らし、壁に十回も頭突きをくれてから受話器をとった。
フロントマンは怒鳴り返す気にもなれぬほどの文化的な声で言った。
「――大日本雄弁社の荻原様がご面会です」
ぼくは静かなバリトンで答えた。
「はい。今おりて行きます。ロビーで待たせて下さい」
浴衣とスリッパでロビーに降りて行けないのは、山の上ホテルの唯一の欠点である。
着替えをしながらフト考えた。オギワラという名の編集者は知らない。おおかた新入社員に差し入れの弁当でも持たせて寄こしたのだろう。
神の配慮により、ホテルの従業員はぼくが大日本雄弁社の原稿を書いていることを知っている。すなわち、牢屋番の配慮により、ホテルが取り次ぐ訪問者は、同社の編集者とぼくの家族だけだ。いちおう家族と呼ぶが、そのうちわけは青山のマンションに同居する義母兼家政婦の富江と、柏木のボロアパートに飼っている恋人兼サンドバッグの「パープーお清」こと田村清子である。富江は毎朝十時きっかりにパンツの替えを持ってやってくる。ついでにそっと睡眠薬と精神安定剤の数を調べて帰る。清子は夜の十時きっかりにやってきて二、三発はり倒され、ついでに凌辱されて帰る。
エレベーター前の大時計は午後九時三十分をさしていた。じきに清子がやってくるだろうから、雄弁社とは面倒な話はせず、弁当だけひったくって追い返すとしよう。
ロビーでは獄中の小説家が何人か、思いつめた顔でコーヒーを飲んでいた。
革張りの古い応接セットに、齡のころなら二十八、九歳とおぼしき女性編集者が、痩せた背を伸ばして座っていた。どうしてそれが編集者だとわかるかというと、つやのないパサパサの髪をうなじでひっつめており、化粧ッ気のない硬質の顔に、牛乳ビンの底を並べたようなメガネをかけているからである。
女はぼくに気付くと、ちょっとおろおろした感じで立ち上がり、最敬礼をした。ホテルの従業員たちは神のごとくフロントの中で微笑み、あるいは牢屋番のごとく玄関の両脇に立っていた。
「お忙しいところ、申しわけありません」
と、女はもういちど深々と頭を下げた。はて、新人ではなさそうだし、弁当も見当たらない。どうしたことであろう。
遠目にはひどい醜女に見えたが、存外美人である。いったい何の因果でパーマ屋にもブティックにもメガネ屋にも行かないのだろうとぼくは思った。
「して、ご用件は?」
ぼくは脂じみた縁なしメガネをハンカチで拭いながら訊ねた。
「木戸孝之介先生ですね」
女は勧められるままに古い革椅子に掛けると、低い、切迫した声で言った。今さら何を言うのだろう。男だったらたちまち躍りかかって首を絞めるところだが、そうもいくまい。早いとこ追い返して、明日は一日じゅう編集長あてに無言電話をかけ続けてやるとしよう。
「いかにも、木戸ですが」
メガネをかけ直すと、視野が明るく開けた。女は思いつめた表情でぼくを睨みつけている。
こいつは雄弁社の社員ではない、と気付いたとき、総身がざわりと鳥肌立った。女はまちがいなく、雄弁社の編集人を騙って忍びこんだ何者かだった。
古い窓の外に風は蕭々と鳴っていた。
ぼんぼりのようなランプシェードに、白い、硬質の顔を晒して、女はじっとぼくを見つめている。ぶ厚いメガネが光を反射して表情は掴めないが、それは明らかに標的を追いつめた刺客の顔だった。
「だ、だれだね、君は。名乗りたまえ」
女はぼくを睨みすえたまま、ハンドバッグの口金を開けた。
極道小説のリアリティを維持するために、実在の親分を何人も登場させてしまっているのだから、いつかは危ない目に遭うこともあろうと覚悟していた。しかし出版社を脅すでもなく、マンションのガラスを割るでもなく、いきなり女の刺客に襲われようとは思ってもいなかった。
それにしても、クラシックホテルのロビーで、美しい刺客にベレッタの銃弾を見舞われて死ぬとは、何とドラマチックな結末だろう。業績はともかく、死にざまだけはヘミングウェイばりだ。〈仁義の黄昏〉シリーズは爆発的に売れ、既刊八冊の版元である丹青出版はきっと烏森のオンボロビルを畳んで、新橋駅前に立派な新社屋を建てることだろう。せめて一年以上もほっぽらかしてある九巻目を、完結させておけばよかったとぼくは心から悔やんだ。
ぼくは月のうち一週間か十日を、神田駿河台にある「山の上ホテル」で過ごす。
そう、昔から文化人の宿として有名な、そして現実にいつ行っても小説家の二人や三人はカンヅメになっている、あのクラシックホテルである。
べつに伊達や酔狂ではない。遁世して小説を書くにはまことに適した場所だからそうするのである。
東京のどまんなかにあるのに極めて閑静で、大学の図書館や古本屋街が近いから、とっさの資料調べにも事欠かない。小ぢんまりとしたサイズは落ち着くし、何よりもホテル側に、締切りに追われてカンヅメになっている作家に対する十分な配慮がある。いわば牢屋番としての配慮である。「文化人の宿」という伝統的なコンセプトがそれほど徹底しているというわけだ。たとえば近ごろ気付いたことなのだが、ここの従業員たちは客がカンヅメになって書いている原稿がいったいどこの出版社の依頼によるものかということまで知っているらしい。
業界の情報を把握しているのか、一読者としての推測であるかは知らない。だがともかく、ぼく自身が予約し、ひそかにチェックインし、自発的にカンヅメとなっていても、なぜか原稿の依頼主を知っているらしいのである。
この点はまさに神の配慮と言えよう。
古いホテルの窓に凩の鳴く夜のことだった。
ぼくはそつなく用意された作家専用の大机に向かって、〈哀愁のカルボナーラ〉のクライマックスに挑んでいた。
それは〈仁義の黄昏〉シリーズの大ヒットにより極道作家の烙印を捺されてしまったぼくが、アイデンティティーの回復を賭けて世に問う、ぶっちぎりの恋愛小説である。
なにしろヨーロッパに留学中の女性ヴァイオリニストが、かつての恋人である新聞社特派員と、ベネチアのサン・マルコ広場で偶然出会い、たちまち焼けぼっくいに火がついて地獄の恋に堕ちてしまうというのだ。
原稿の半ばまでは、すでに大日本雄弁社の編集者に渡してある。半ばといったって五百枚もあるから、先方が気に入ろうと気に入るまいと、もはや取り返しはつかない。
もちろんヤクザの出番はなく、銃声も聴こえず、お得意の法的医学的用語を駆使した露骨なセックス・シーンもない。古今の恋愛小説の定義に従い、物語はさしたる盛り上がりもなく、ただ哀しく美しく、ダラダラと進む。
数日後、件の編集者がすっ飛んできて、「そろそろマフィアが出てきますよね、そうですよね」と言ったので、すかさずバックドロップを決めてやった。
クライマックス・シーンは、ヴァイオリニストと新聞記者がたそがれのゴンドラに乗り、夕日に染まった「溜息の橋」の下で熱いくちづけをかわすのである。
――古いホテルの窓に凩を聴きながら、ぼくはうっとりと、恋人たちをいざなう船頭になっていた。
電話が鳴った。
ぼくは呪いの雄叫びを上げて原稿をまき散らし、壁に十回も頭突きをくれてから受話器をとった。
フロントマンは怒鳴り返す気にもなれぬほどの文化的な声で言った。
「――大日本雄弁社の荻原様がご面会です」
ぼくは静かなバリトンで答えた。
「はい。今おりて行きます。ロビーで待たせて下さい」
浴衣とスリッパでロビーに降りて行けないのは、山の上ホテルの唯一の欠点である。
着替えをしながらフト考えた。オギワラという名の編集者は知らない。おおかた新入社員に差し入れの弁当でも持たせて寄こしたのだろう。
神の配慮により、ホテルの従業員はぼくが大日本雄弁社の原稿を書いていることを知っている。すなわち、牢屋番の配慮により、ホテルが取り次ぐ訪問者は、同社の編集者とぼくの家族だけだ。いちおう家族と呼ぶが、そのうちわけは青山のマンションに同居する義母兼家政婦の富江と、柏木のボロアパートに飼っている恋人兼サンドバッグの「パープーお清」こと田村清子である。富江は毎朝十時きっかりにパンツの替えを持ってやってくる。ついでにそっと睡眠薬と精神安定剤の数を調べて帰る。清子は夜の十時きっかりにやってきて二、三発はり倒され、ついでに凌辱されて帰る。
エレベーター前の大時計は午後九時三十分をさしていた。じきに清子がやってくるだろうから、雄弁社とは面倒な話はせず、弁当だけひったくって追い返すとしよう。
ロビーでは獄中の小説家が何人か、思いつめた顔でコーヒーを飲んでいた。
革張りの古い応接セットに、齡のころなら二十八、九歳とおぼしき女性編集者が、痩せた背を伸ばして座っていた。どうしてそれが編集者だとわかるかというと、つやのないパサパサの髪をうなじでひっつめており、化粧ッ気のない硬質の顔に、牛乳ビンの底を並べたようなメガネをかけているからである。
女はぼくに気付くと、ちょっとおろおろした感じで立ち上がり、最敬礼をした。ホテルの従業員たちは神のごとくフロントの中で微笑み、あるいは牢屋番のごとく玄関の両脇に立っていた。
「お忙しいところ、申しわけありません」
と、女はもういちど深々と頭を下げた。はて、新人ではなさそうだし、弁当も見当たらない。どうしたことであろう。
遠目にはひどい醜女に見えたが、存外美人である。いったい何の因果でパーマ屋にもブティックにもメガネ屋にも行かないのだろうとぼくは思った。
「して、ご用件は?」
ぼくは脂じみた縁なしメガネをハンカチで拭いながら訊ねた。
「木戸孝之介先生ですね」
女は勧められるままに古い革椅子に掛けると、低い、切迫した声で言った。今さら何を言うのだろう。男だったらたちまち躍りかかって首を絞めるところだが、そうもいくまい。早いとこ追い返して、明日は一日じゅう編集長あてに無言電話をかけ続けてやるとしよう。
「いかにも、木戸ですが」
メガネをかけ直すと、視野が明るく開けた。女は思いつめた表情でぼくを睨みつけている。
こいつは雄弁社の社員ではない、と気付いたとき、総身がざわりと鳥肌立った。女はまちがいなく、雄弁社の編集人を騙って忍びこんだ何者かだった。
古い窓の外に風は蕭々と鳴っていた。
ぼんぼりのようなランプシェードに、白い、硬質の顔を晒して、女はじっとぼくを見つめている。ぶ厚いメガネが光を反射して表情は掴めないが、それは明らかに標的を追いつめた刺客の顔だった。
「だ、だれだね、君は。名乗りたまえ」
女はぼくを睨みすえたまま、ハンドバッグの口金を開けた。
極道小説のリアリティを維持するために、実在の親分を何人も登場させてしまっているのだから、いつかは危ない目に遭うこともあろうと覚悟していた。しかし出版社を脅すでもなく、マンションのガラスを割るでもなく、いきなり女の刺客に襲われようとは思ってもいなかった。
それにしても、クラシックホテルのロビーで、美しい刺客にベレッタの銃弾を見舞われて死ぬとは、何とドラマチックな結末だろう。業績はともかく、死にざまだけはヘミングウェイばりだ。〈仁義の黄昏〉シリーズは爆発的に売れ、既刊八冊の版元である丹青出版はきっと烏森のオンボロビルを畳んで、新橋駅前に立派な新社屋を建てることだろう。せめて一年以上もほっぽらかしてある九巻目を、完結させておけばよかったとぼくは心から悔やんだ。